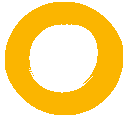| 同じ年頃の同僚たちと話しがまとまり、母たちは畑で育ちかけのカボチャを早々と収穫して、学校の実験室で煮てぜんぶ食ったそうだ。(そんな無茶をことをしても、きっと叱る上司もいなかったのだろう。男たちはみな出征中か疎開中。ただ一人いばっていた軍事教練の教官も、敗戦と聞くや尻に帆かけてどこかへ逃げてしまったらしい。) まだ十分に熟していないカボチャは、水気がなく、とてもまずかった、と母はいう。 8月。窓の外には青空と入道雲。その向こうから何がやってくるかを不安げに見やりながら、なかばヤケクソでカボチャを頬張る母たち。若い娘たちのことだ。将来のことよりも、彼女らはまず何よりもお腹が減っていて、カボチャを早く食べたかったのだろう。 夕暮れ。川の面に遠くの花火が映っている。母とわたしはスカートの裾をたくしあげ、川の水にそっと足をひたす。水底の小石の、ぬるりとした感触がわたしたちを立ちすくませる。でも、引き返すことはできない。 向こう岸は、闇に浸っている。流れの途中で足をふんばって、目印の旗を振っている人もいるが、誰もその人に目をやろうとしない。みんな黙々と、それぞれにあたりを見回しながら、ゆっくりと川を渡っていく。 |