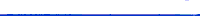
|
|
| |
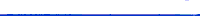
|
|
|
05 featuring...
|
この連載でも紹介したことのある伊藤芳博氏らの同人誌「59(ゴクウ)」が先頃第15号をもって終刊した。創刊当初より5×9で45才になったら終わりにしようということになっていたらしく、予定通りの終刊である。 この雑誌は誌名にもあるように1959年生まれの三人の同人から成る同人誌で、世代にこだわっているところが特徴であった。伊藤氏は岐阜、岩木誠一郎氏は札幌、金井雄一氏は神奈川と地域はばらばらで、ほとんど直接には会ったこともないらしい。世代にこだわるということについては賛否の両論があるが、おもしろいコンセプトだったと思っている。 終刊号に寄せた文章の中で田野倉康一氏が書いているように、そこにあったのは、「特に70年代の前半の、詩におけるミニマリズムとも言うべき動向の中で、たしかに見失われてしまっていたある種の詩の豊かさを、まさにその良質の抒情によって回復し、さらにはその向こうへ道を開こうとするその詩業」であったとおもうからだ。 そしてそうした営為はゴクウの同人たちだけではなく、例えばこの原稿でこれまで取り上げてきた小池昌代氏にも、四元康祐氏にも見いだすことができるように思う。不思議なことにこれらの詩人たちは皆1959年生まれだ。もちろん世代論で早急に何かを語ったつもりになることの危険性を承知しつつも、この一致に気づいたときの軽い驚きがこの原稿をスタートさせるひとつのきっかけになっていることは間違いない。これは何なのだろう。もちろん同じ世代に属していながらも全く違う傾向の詩を書いている人もいるわけだから、このことで全てのことが語れるわけではないが、正統的な叙情詩の技法を用い良質の抒情を紡いできた詩人たちの場合、その成果が現れるのはどちらかと言えば遅く、ようやく今になってその成果がゆっくりと現れつつあると言えるのではないかと思うのだ。 では正統的な抒情の詩とはどんなものかと言えば、ゴクウの詩人たちの中ではまず岩木誠一郎氏を挙げるのが良いのではないかと思う。岩木氏には『夕方の耳』という優れた詩集があるが、まずは巻頭の詩を引いてみよう。
電話の相手はありがちな質問を投げかけてくる。「そちらへはどのように行けばよいのでしょう」とか「目印になるものはありませんか」とか。そのたびに詩人は内省を始める。「そちら」とは何か。「目印」とは何か、と。現実からふと離れて非現実の世界に入っていくその技法は、典型的な抒情詩の展開例であろうと思うが、実にしっかりとした筆致であり、思わず読者は詩人の内省の中に引き込まれる。 贅言を弄するより詩をもう一編引用しよう。詩集の表題作である。
バスに乗っているというシチュエーションの中で、詩人は再び内省に入り込む。聞こえているのはエンジン音。それだけが微かに現実と内省をつないでいる。詩人は行き先を告げることさえ忘れている。そして遊星という言葉の艶やかな響きとイメージ、さらに耳という身体的部位の感覚表現が詩を閉じる。 この遊星という言葉は「不意に」浮かぶ。「不意」というところがポイントだ。清岡卓行は「ふと」という副詞を多用した。逆に吉岡実は、「ふと」という言葉を使うことを自らに戒めた。このエピソードは二人の詩人の書法の違いを明白に示していると思うが、明らかに岩木誠一郎は前者の部類に属している。 岩木誠一郎は、詩は常に不意にやってくると言っているかのようだ。 (「月刊ポエマホリックカフェ」2004年4月号より転載) |
||||||||||||