|
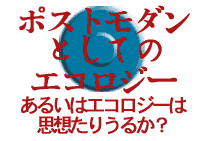
text/金水 正 
私たちはエコロジーをやり過ごすべきなのだろうか?
エコロジーとは思考するに足りぬ抽象的な無駄話であるとして、打ち捨てておくべきものなのだろうか?
|
イデオロギーとしてのエコロジー
私の不確かな記憶からいえば、サルトルはマルクス主義を現代人にとって 不可避なアポリアであるといった。どういう文脈でサルトルがこういったの
かいま確かめることができないし、そもそもこのとおりにサルトルが語った のかどうかも確信がないが、サルトルがこう語ったその当時のニュアンスは
理解できるような気がする。当時存在した東西間の緊張と資本主義がかかえ るさまざまな問題が、サルトルにそれを思考することを不可避に強いたし、
なおかつそれは簡単に解決のつくような問題ではなかっただろう。
サルトルにとって、マルクス主義がそう表れていたように、われわれの前にいま「エコロジー」という怪物がそう表れているように思える。まずエコロジーについて考えることはわれわれにとって不可避なことのようである。確実に地球の環境は汚染され続け、化石資源は消耗し続け、生物の種は死滅して減少し続け、にもかかわらず人類は増え続けているから。次にエコロジーに関して絶対的な解決策はないと思われる点において、それはアポリアである。人類の現在の活動は地球の資源を消費することによって成立している。もし環境の保全を第一義に考えるとするなら、大幅に人間の活動を縮小させる必要があるだろう。現状は縮小どころか、それを拡大することを前提にわれわれの生活は成り立っている。では誰が、どのように、そしてどれぐらいの規模で必要なコントロールを行うのか。それが簡単な作業でないことは誰にでも想像がつく。
ところで、サルトルの実存主義と、ここで語られているマルクス主義と、そしてエコロジーとの間には関連があると『現代思想はいま何を考えればよいのか』の橋爪大三郎は書いている。
かつてのマルクス主義は、1科学性、2全体性、3宗教性、の3つをかねそなえて人々を吸引していた。しかし60年代から70年代にかけて、各国の共産党の指導力が低下してさまざま批判がまき起こり、マルクス主義が与える大きな物語の書き割りにひび割れが生じる。その時、登場したサルトルの実存主義は、マルクス主義の与える歴史的な意義という大きな物語の中に自分の身を置き切れない(そこに割り切れない)ひとりひとりの実存を支える「すきま思想」になったと橋爪はいう。
60年代の末からは日本でも構造主義が流行り始める。構造主義は「歴史」そのものを相対化してしまう。「歴史」そのものが「近代」のものであり、「西欧」のものであり、それに対して「未開」とされていたものを分析し、その両者の間に無意識に想定されていた優劣を相対化することによって、構造主義は「マルクス主義」も「近代主義(資本主義)」もともどもに解除してしまう。
両者をともどもに解除することによって、かつての左翼にマルクス主義からの撤退を受け入れやすいものにすることが「構造主義」の効用であったのだという。
70年代に入ると、マルクス主義の退潮と入れ替わりに、公害や環境破壊に人々の関心が向くようになる。自然保護やエコロジー運動の流れの中に、資本主義にかわる新しい社会のイメージを求める人も多くなる。この感覚はじつはマルクス主義に通じていると橋爪はいう。マルクス主義が資本主義から脱出する物語だったように、エコロジーも産業文明からの脱出の物語であるという意味で同様なのだと。
かつてのマルクス主義がそなえていた科学性、全体性、宗教性のうち、構造主義が科学性と全体性をひき継ぐとするなら、エコロジーは全体性と宗教性を引き継いでいる。宗教性を引き継ぐエコロジー運動ほど夢物語に近づいていく。
80年代に入ってしばらくするとポスト・モダン(ニュー・アカデミズム)旋風が吹く。ポスト・モダンを受容した人々にとっては、資本主義はもはや否定する必要もない日常になる。(「マルクス主義の瓦礫を越えて」)
この文章を書いている私は、サルトルの実存主義から、構造主義、そして記号論といったいわゆるポストモダン思想の流れをくぐってきた。流行として考えれば、私の浪人時代にサルトルはもう読まれなくなりかけていて(しかし浪人時代とは実存主義に似つかわしい時代だった)、むしろ私の大学時代に来日したクロード=レヴィ・ストロースが新たな話題を呼んでいった。文学部の学生だった私もご多分にもれずそうした流れを追いかけて本を読みついでいった。
大学を卒業して就職し、バブルがはじけて、ベルリンの壁が破れ、そうしてすべてが吹き過ぎていってしまった後のようないまの状況のなかで、それでもわれわれが学び、いまでも通用すると思っているいくつかの教訓があったと私は考えている。それはたとえば、あるスローガンが絶対的な真理のような顔をして表れてきたときにはそれはイデオロギーであり、疑ってかかれというようなことだ。
いまエコロジーの考え方は、われわれ人類全体にたいして誰でもが妥当し、誰でもが守るべき真理のようにして表れている。ほかならぬこうした事態が生じているときに、私の経験は私にこうささやくのだ。これはうさんくさい、疑ってかかれ、と。実際のところ、われわれはエコロジーにどう対処していいものか分からない。仮に自分の身の回りにあることから環境に負担のかからぬよう気を付けてみようとしたところで、何をすることがどの程度環境への負担を減らすことになるのかがわからない。それどころか槌田敦の『環境保護運動はどこが間違っているのか?』によれば、例えば牛乳パックを回収する消費者の環境運動は、すでに存在していた古紙回収業者を営業的に窮地に追いやることによってかえって環境に悪影響を与える結果を招いているという。仮に槌田の言葉を信じるとした場合にここで表れている事態、抽象的な真理とそこから導き出される真偽の定かならない具体的な行動との間の落差こそ、私たちがイデオロギーと呼んできたことがらではないか。
こうした場合に、われわれの経験が教えている対処の方法とは、「やり過ごす」ということだ。抽象的な問題をわれわれが等しく不可避の問題として考えなければならないという理由はない。問題というものは、それが具体的に自分の身の回りのこととして物理的な強制力を持って考えることを強いてきたときにようやく考える必要性を持つ。そのような時がやってくるまで、できるだけ「やり過ごして」いることが事の正しい対処のしかたであると私たちは教えられてきたように思う。
であるとするなら、私たちはエコロジーをやり過ごすべきなのだろうか?エコロジーとは思考するに足りぬ抽象的な無駄話であるとして、打ち捨てておくべきものなのだろうか?
そうした態度こそが「ポスト・モダニスト」の最たる姿勢であると断じる、懐かしい学生時代に左翼だったあの某の顔が、いま浮かんでくるようだ。
ポスト・モダンは思想を解体することによって結果的に現状追認を行う。それは権利の放棄によるある種の自殺行為ににていると、彼はそんな言い方はしないだろうか?
しかし時代は確かに転換している。いまエコロジーとして語られている言葉もまた、もはや単純な反体制(資本主義に対する批判)ではありえない。「持続可能な発展」という大合唱がその主流を成している。

|



