筆者が小学生の時分、国語の時間などに書いた作文でデキのいいのがあるとキープしておき、学区全部の作品を半期に一度まとめて1冊の文集として発行していた。それは低学年用と高学年用に別れていて、名前を『ひろっぱ』(小学校児童文詩集)と言った。
この作文集、残念ながら筆者は掲載されたことがなかったのだが、どの作品もけれん味なく、その心情や出来事がストレートに活写されていて、読んでいて新鮮で思わず大笑いさせられる傑作ぞろいなのだ。
この『ひろっぱ』から傑作を2編、紹介したいと思う。小学生の作文なので、漢字が少なくやや読み辛いが、つづり等々はあえて原文のままにした。
小学4年生の部 『遠足(奈良方面)』 N.K.
シンプルなタイトルだが、壮絶な内容が記されている。遠足といえば、バス ツアー。そしてバス ツアーと切っても切れないのが…
◆
わたしたち四年生は、五年生といっしょに10月13日奈良方面ヘ観光バスの二号車に乗って遠足へ行きました。
行きしな香取さんや、稲垣くんがあげました。わたしは、バスによう子はかわいそうだなと、思いました。それから歌を歌ったり、なぞなぞをしたりバスガイドさんが、話をしてくれたりして、法隆寺へつきました。
<中略〜ここから寺社仏閣を見学してまわります〜>
それから、わたしたちのまっていたおべんとうになりました。わたしは、香取さんと、中居さんと、菊川さんと、藤原さんと、伊東さんといっしょにおべんとうを食べました。
わたしは、おなかもへっていたし、見はらしがよくてとてもけしきがいいのでおべんとうが、とてもおいしかったです。でも香取さんは、気分がわるかったのでほとんど食べませんでした。
<中略〜ここからさらに東大寺を見学してまわります〜>
そして、ほかにいろいろな物を見て、大仏でんをでてしゃしんをうつしてから、バスのところまで行きました。
そして、バスは発しゃしました。帰りも、香取さんや、木村くんがあげました。
それから、流行歌を歌ったり。マンガの歌を歌ったり、ふつうの歌を歌ったり、おかしのかえっこをしたり、おかしを食べたりして、バスはM市へつきました。そしてそこでかいさんしました。
<後略>
◆
<鑑賞のポイント>
この作品の作者N.K.さんにとっては、とっても楽しい遠足だったのでしょうが、お友達の香取さんには地獄のバス ツアーだったでしょうね。あえてお昼ご飯を食べなかったのに、帰りもゲロったのは凄い。そのあたりを作者は実に淡々と描写している。ツアー開始2行目でいきなりゲロ描写に入るのも凄いが、帰りのバスではもはや何のフォローもなく、何事も無かったかのように歌を歌いまくっているのも凄い。
小学5年生の部 『ああ かっつんが』 K.E.
当時はまだまだ、自然が至るところに残っていたのだ。悪童二人が崖で遊んでいて、大変な事件に巻き込まれる。かっつんと呼ばれる少年が、崖から墜落して行く場面の描写も凄いが、墜落の原因はもっと凄い。
◆
<前略>
そのがけは五メートルぐらいの高さで赤土が、いまにもくずれそうでした。下へ行ってす手でのぼると、ボコボコジャラジャラと、上からすなが落ちてきました。
<中略〜最初に作者のK.E.くんが登ろうとするが、失敗して下へ落ちる〜>
いよいよこんどはかっつんのばんです。かっつんのときは、そこらに落ちていたつるはしにつるを五本くくり、岩につるはしをうちつけました。かっつんはうれしそうにがけの下にまわりました。ぼくは、心の中で、(かっつんこんど落ちるばんや、おもろ)と思いました。
かっつんは、顔を赤くして、ほっぺたをふくらませて上へ一だん一だんがけをけずってのぼってくる。もう一歩で上やのに、というところでぼくが、すなをシャラシャラと落としてしまいました。そのとたんかっつんはズバババズボとがけから足をすべらせて、手もつるからすべらせてちょっと落ちかけました。
ぼくは、一しゅんヒヤッとして、「いけるか かっつん。」 と、聞くと「いける、いける」と、元気な声が返ってきました。 ぼくの時は、落ちたので少しくやしくなってきました。一しゅん悪い考えが頭にうかんできました。はなしたら落ちよるかなと思って、ぼくの持っていたつるはしをパッとはなすとすなが、ひびをつくってくずれ、つるはしのぬけたあながほれました。
「あっ、落ちるぞ。かっつん。」「つるはしが。くずれるど。」 と、ぼくがさけぶと同時に、「アー。」と、高い所から落ちるようにさけびながら、かっつんがつるといっしょにさかさになりそうに、落ちました。上から、ガサガサカシャカシャ、カチコチとすなや石がかっつんにあたりました。さいごに落ちたつるはしが消えたと思ったらかっつんの頭の上に見えて、かっつんの頭に当たってしまいました。ひどいいきおいで当たったんでしょう、当たったとたん、うしろにかっつんはゆらつきました。
「いたいいたい、死ぬ死ぬよおァーいたいいたい。」 と顔をまっかにしてまるできちがいのようにさけびました。頭をりょう手でおさえじっとしておられないほど痛がっています。「いけるか。」ぼくはがけの上からのぞきこんで聞きました。「う、うん。」 と、もう死ぬまぎわのように静かに言いました。ぼくは、はじめはおもしろいと思っていましたが、だんだん心配なってきて、「帰ろか。」 と、かっつんにささやくと「お、帰ろ。」と、頭をおさえて元気なさそうに言いました。帰りしなもかっつんはもう死にそうな顔で頭をおさえていました。ぼくは心の中でほんまに死にそうかなと思いつづけました。
◆
<鑑賞のポイント>
「いたいいたい、死ぬ死ぬよおァーいたいいたい。」の小さいアが何とも素晴らしい! 小学生らしからぬ擬音の連発も見事と言えるでしょう。しかし、筆者が初めて読んだ小五の時以来、このかっつんという少年のその後が気になってしょうがない。彼はその後どうなったのか?
たぶん何事も無かったかのように普通に大人になっているのだろうけれど(笑)
この作文は彼もきっと読んだだろうから、事故の真相を知ってどう思ったのだろうか? 実際、当時の担任の先生が読んで、選んで、文集として発行されたわけだからその経緯を考えるだけでも、これはメチャクチャ凄い。 ![]()
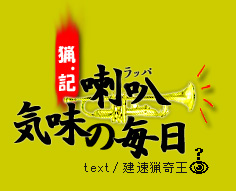
[猟奇的な小学生の日記]
昭和の時代のおおらかなお話
小学校児童文詩集
『ひろっぱ』より


