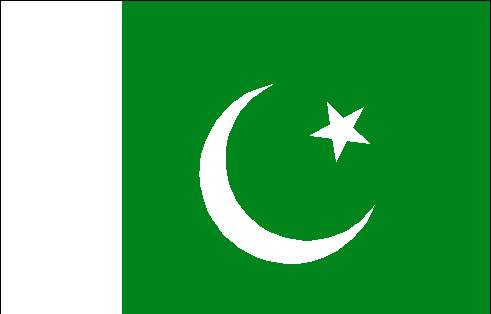『燃えよ! カンフー』は'72年から3年間に渡りABCネットワークで放送されたTVシリーズである。流れ者のガンマンを拳法の達人に置き換え、禅問答などを中心に“東洋の神秘”をフィーチュアした哲学的西部劇とでも呼ぶべきストーリーは高い評価を受け、米テレビ芸術科学アカデミー(The Academy of Television Arts & Sciences)主催のエミー賞において監督賞・撮影賞を受賞した。
修業時代のケインと師範である僧との様々なエピソードが回想シーンとして挿入され、二つのドラマが同時進行するユニークな作劇スタイルが取られている。
主人公が白人と東洋人の混血児という設定上、移民としてアメリカにやってきた東洋人、滅ぼされつつあったネイティヴアメリカン(以下ネイティヴ)などマイノリティにスポットをあてたエピソードに傑作が多い。物語の随所に現れるレイシズムとそれに対して静かに、しかし深い信念を持って対処するケインの姿に共感を覚えたファンは多かったはずだ。
合衆国のテレビ業界におけるスポンサーの意向は絶対で、それにそぐわないもの、視聴率が振るわないものは問答無用で打ち切りになる。その意味で3年間もの長きにわたって放送され、また正式な形での最終回(さらには特別編や続編まで)も存在する以上、スポンサー・視聴者の双方から支持を得ていたということになる。
こうした問題意識の高い良心的な作品をメジャー資本が制作し、それが支持されていたことは正に奇跡と言って良い。少なくとも現在の業界に同じことを期待するのは無理な話で、やはり時代が良かった としか言いようがない。
斜陽化する映画産業がその状況を打破するため、新進の作家に規制の少ない制作環境を与え、それが実に理想的に展開したのが、例えば'60年代後半から'70年代初頭の “アメリカンニューシネマ” ムーヴメントであるが、こうした良いムードが現場にもまだまだ残っていたのだろう。
ゲストも豪華で、当時子役であったジョディ・フォスター(この時のジョディこそ筆者の初恋の人である)、若手俳優時代のハリソン・フォード、『宇宙大作戦/スタートレック』のウィリアム・シャトナー、『裸の銃を持つ男』のレスリー・ニールセン、『マイアミ バイス』のドン・ジョンソン、そして俳優一家キャラディーン家からはデイヴィッドの父ジョン、兄弟のキースやロバートも登場している。
◇
ストーリー1870年代… クワイチャン・ケイン(デイヴィッド・キャラディーン)は、清(中国)でアメリカ人の父と中国人の母の間に生まれた。ケインは幼くして両親を失うが、運よく少林寺に入門でき、師範である僧たちから精神の調和のための東洋哲学と非暴力の規律を学ぶ。
肉体を極限にまで高める修行を通じマスターとなったケインは少林寺を去り、俗世の人間となったが、ある時、恩師を助けようとして王族の一人を殺めてしまい、お尋ね者となる。ケインはゴールド ラッシュに沸くアメリカ西部に逃げ延びるが、そこでは賞金稼ぎや人種差別等、様々な試練が待ち受けていた。
◇
'73年12月に公開された『燃えよドラゴン』の大ヒットに便乗する形で、90分のパイロット版が'74年秋、児玉清解説の『土曜映画劇場』(テレビ朝日系)で放送された。放送日を指折り数えて楽しみにしていた筆者を茫然自失(背中一面にでっかい掌の絵が描かれたゴールドの道着−このファッション センスだけでもドン引き)させた後、同系列で深夜、シリーズの放送が開始される。当時、ブルース・リーの神がかり的なマーシャルアーツに傾倒していた筆者は、デイヴィッド・キャラディーンのしょっぱいアクションシーンには閉口していたが、その精神性のレベルにおいて大いに評価していた
原案はブルース・リーだったが、その風貌があまりにも東洋人だったため配役からはハズされた とも言われている。しかしDVDに収められた特典映像を見る限り、そういった証言はない。
ただ、本編以降に制作された外伝でブルース ジュニアのブランドンと共演したり、ブルースがジェームズ・コバーンと企画した幻の作品『サイレント フルート』に主演する等、キャラディーンとブルースの関係は意外にも深い。
◇
第16話:『憎しみは愛に焼かれた』 THE ANCIENT WARRIOR
では第一回目にあたり、全63本製作されたシリーズ中、筆者にとって最も印象的なエピソードを紹介したい。『燃えよ! カンフー』はエピソードそれぞれの完成度が高いため、単に物語を追うだけでも十分その魅力は伝わると思う。従って筆者のコメントは、蛇足でしかない。
このエピソードでは珍しく、修行時代のケインが登場する回想シーンがなく、カーン先生との会話を思い出すだけにとどまっている。
***
“先生、愛する者を失った時は、どうすればいいのですか?”
“まことの愛は決して失われることがない、と知るがよい。死んだ後でこそ、初めて絆の深さがわかるものだ。そして生前よりもより強く、その人間と一つになることが出来る”
“それは長い間知っていて、愛した人の場合だけ、そうなるのでしょうか?”
“時には、ほんのつかの間の巡り逢いにおいて互いの魂を永遠の絆で結ぶ者もある”
“行きずりの未知の人であっても、それは可能でしょうか?”
“魂の世界には、時間の長短はないのだ…”
***
サンタフェへ向かうケインは、山中の交易所で年老いた酋長ビッグイーグルと出会った。老酋長は死期を迎えるに当たり、“生まれた土地で死ななければ、あの世に生まれ変われない”というネイティヴの言い伝えに従って、息子に連れられ故郷へ帰る途中だった。ところが、具合の悪かった息子の様子を見たケインは表情を曇らせる。息子はすでにこと切れていた。残された老酋長の頼みで、ケインは予定を変え、老酋長を故郷まで送り届けることにする。
たどりついた谷間の町で、老酋長は自らの埋葬の地を見出すが、そこは町の真ん中にある大きな木の下であった。しかも、その町では8年前、ネイティヴの為に14人の白人が惨殺されるという事件があり、それ以来、人々はネイティヴに対して異常な憎しみを持っていた。
***
本来、北米大陸はインディアンという誤った名称で呼ばれたネイティヴたちのものであった。幼い頃から、勇敢な保安官や騎兵隊の大活躍が野蛮な原人を駆除するストーリーばかり見て育った筆者が、この白人の都合だけで描かれた矛盾に気づくには、ずいぶん時間がかかった。正にこの『燃えよ!カンフー』のエピソードによって、片目が開いたと言っても過言ではない。
頭の皮を剥ぐ、まぶたを縫いつけて炎天下に放置し失明させる… 一般的な西部劇ではおなじみの残忍非道だが、では何がネイティヴをこのような行為に走らせるのか? ということについて、多くのドラマはその理由を明らかにしていない。あえて言えば、それが彼らの本質である ということか。結局、野蛮な原人は無意味な残虐行為を繰り返し、白人とは理解し合えない忌むべき存在として、フロンティアラインを西へ進めていく中、駆除すべき邪魔者としてのみキャスティングされている。
ところが一方で、コロンブスの率いた探検隊はこの野蛮な原人とセックスし、梅毒をヨーロッパに持ち帰っている。性欲においては、野蛮な原人というレイシズムもたちまちノー問題なのだからいい加減なものである。
ところで話は変わるが、デストロイヤーのフィニッシュホールドとして有名なプロレスの技 4の字固め(フィギュア4レッグロック '60年代におけるプロレス四大必殺技の一つ。ちなみに後の三つは、ブルーノ・サンマルチノのベアハッグ、ボボ・ブラジルのココバット、ルー・テーズのバックドロップ)は、ネイティヴが白人を拷問する際、実際に使った技の一つである。こうした経緯からかネイティヴ系のレスラーにはこの技をフィニッシュホールドとしている選手が多い。最も有名な選手は、第48代NWA世界ヘビー級王者 ジャック・ブリスコである。
***
埋葬の地と定めた木の下で休息を取っていた老酋長に町の若者(バカ者?)が乱暴を仕掛ける。あと一日かもって二日の寿命である老人にさえ、その憎しみは向けられるのだ。しかし、ケインは彼らをあっさりやっつけてしまう。
“死ぬことが望みですか?”“あの世に生まれ変わることが望みだ”
日頃からこうした状況を憂えていた判事は、市長に迫って市の委員会を召集、老酋長の希望は正当なものであり、町全体の土地の所有権と引き換えに、老酋長の埋葬を認めてはどうか という提案をする。
委員会で一人の青年がネイティヴへの憎悪をまくしたてる。青年は8年前の事件で弟を殺されていたのだ。老酋長は静かに諭す。
“なぜお前の心には憎しみしかないのだ? …それは白人の側だけを見た、白人の歴史だ。そこには最初に殺された14人のわしの仲間のことは記されていない。さらに一週間後に、騎兵隊に皆殺しにされた男、女… そして子供達… それら67人のことも白人の歴史には何も記されていない。
どうして過ぎた事は忘れようとせんのだ? 相手を許すことで自分も救われるのだ。わしはそうした”
採決の末、一票差でこの提案は可決された。
“勝ちました。あなたの埋葬の場所は、もう誰も変えられません”
“空しい勝利だ… この町は憎しみで満たされている。わしを迎えてくれる神の優しい恵みは、もうここにはないのだ。ここにはもう用はない。わしを山の松の林の中で死なせてくれ。そしてお前の手で、わしの遺体を焼いてくれ…”
死期の迫った老人の最期の望みをいとも簡単に踏みにじり、さらにはこうした諦念を強いる感覚が筆者には理解できない。これこそが自由の国と誤認されてきた合衆国の正体である。'70年代初頭、心ある制作者たちは、このことを自覚的に描いてきた。こうした母国の歴史を批判的に描いた作品が、普通にTVで放送され、それが高い評価を受けていたという事実に筆者は驚きを禁じ得ない。
広島と長崎に原子爆弾を投下することで、第二次世界大戦後のイニシアティヴを握り、ついにはアメリカンスタンダード(グローバルスタンダードとはアメリカンスタンダードに他ならない)を確立した合衆国。今やこの国こそ世界最大のテロ国家であり、パワーハラスメントとコンプライアンス違反の温床、正に諸悪の根源である。
被害者の寛容な心にもたれかかる一方、飽くまで合衆国を断罪しようとする人々をパブリックエナミー(実際には合衆国にとって不都合な人々でしかない)として無差別に空爆する恥知らずな現在の政府に、自浄能力を期待することは、もはや間違いなのだろうか。
***
“死んだのか? 悪いことをした…”
“謝ることはありません。酋長はあなたに心から、感謝していました。でもここに葬られることは望まなかった”
“しかし、この場所に葬られることが、酋長の夢ではなかったのかね?”
“新しい夢を抱いて死んだのです。この土地を、憎しみで覆う代わりに、愛で包もうと願ったのです”
“しかし、その願いが、果たして皆にわかってもらえるだろうか…”
“今はわからなくても、ビッグイーグルの物語は、多くの人に語り継がれ、伝えられるでしょう…”![]()
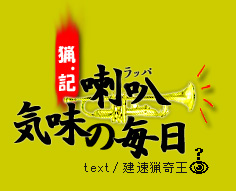
[猟カツ日記]
TVマニアックだった日々
第1回
『燃えよ! カンフー』