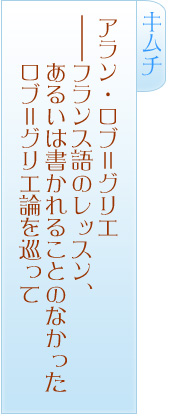![]() Kのささやかな探求を、物語と呼ぶべきなのか、評論と呼ぶべきなのか、単なる戯文と見るべきなのかは判然としない。それは失われたテキストを巡る探求であり、それが一種のクエストであるからには、ごまんとこの世に存在するゲームの一種と考えることもできるかもしれない。はっきりとしているのは、失われたテキストがアラン・ロブ=グリエ論として書かれるはずのものであり、1981年に発表されたロブ=グリエの『ジン』が、はじめアメリカの大学生向けのフランス語の読本として用意されたという話に触発されて構想されたものであるからには、それがいまから早くも三十年近くも前のことになるということであり、そしてそのロブ=グリエ論がついに書かれることがなかったということだけである。したがって、以下に読まれるこの探求の物語が、最初から困難を抱え込んでいることははじめから予想することができたのである。
Kのささやかな探求を、物語と呼ぶべきなのか、評論と呼ぶべきなのか、単なる戯文と見るべきなのかは判然としない。それは失われたテキストを巡る探求であり、それが一種のクエストであるからには、ごまんとこの世に存在するゲームの一種と考えることもできるかもしれない。はっきりとしているのは、失われたテキストがアラン・ロブ=グリエ論として書かれるはずのものであり、1981年に発表されたロブ=グリエの『ジン』が、はじめアメリカの大学生向けのフランス語の読本として用意されたという話に触発されて構想されたものであるからには、それがいまから早くも三十年近くも前のことになるということであり、そしてそのロブ=グリエ論がついに書かれることがなかったということだけである。したがって、以下に読まれるこの探求の物語が、最初から困難を抱え込んでいることははじめから予想することができたのである。
『ジン』は、シモン・ルクールの物語として提出される。全体で八章からなるシモンの物語は、そのテキストが発見された経緯を示すプロローグと、シモンの失踪を巡る後日譚を示したエピローグに挟まれている。このプロローグとエピローグの語り手は、シモンの失踪に何らかの形で関わっているかのようなのだ。そこには明らかに組織の影が在る。
![]() ぼくは指示に従って原稿を書こうとしている。ぼくに指示をした人物は、ぼくが見るとは限らないメールボックスにその指示を書き込み、しかもその指示が自分自身のものではなく、Aの指示であるかのようにさえ振る舞っていたのだ。アラン・ロブ=グリエがこの世を去ったのは明らかなことだ。そしてそのAが、いまから三十年近くも前に、大学のスロープの下にあるサークル室を曖昧な形で占拠したあげくに、大時代的なタイトルの文藝同人誌をきまぐれなサイクルで発刊していた仲間の一人であるからには、その指示が彼の呟きからもたらされたものである可能性は確かに否定できない。Aはきっと、いまごろ同じように締め切りに追われながら原稿を書いているだろう。そしていつものように、締め切りに間に合わず、原稿を落とすかもしれない。しかし、ぼくが、発信者も定かでないその指示にあらがうこともできずにこの原稿を書こうとしているのは、ぼくに直接メールで指示をよこしたその人物に対して、ぼくが負い目をおっているからだ。もともとメールマガジンという形式の同人誌を発行しようと持ちかけたにもかかわらず、その人物にぼくは残りの仕事を押しつけて、いまではめったにメールボックスを開くこともない。しかし、こうした一連の心理描写は、単なる口実だという可能性もある。それ以上に、ぼくがこの仕事に魅惑され、引きつけられていたから、このやっかいな仕事を引き受けたのだという可能性についてぼくは考えてみる。しかし、いずれにせよそうしたいっさいの考察は無意味である。ぼくは指定された時間きっかりに到着する。すべては指示どおりだ。組織の指示にあらがうことはできない。
ぼくは指示に従って原稿を書こうとしている。ぼくに指示をした人物は、ぼくが見るとは限らないメールボックスにその指示を書き込み、しかもその指示が自分自身のものではなく、Aの指示であるかのようにさえ振る舞っていたのだ。アラン・ロブ=グリエがこの世を去ったのは明らかなことだ。そしてそのAが、いまから三十年近くも前に、大学のスロープの下にあるサークル室を曖昧な形で占拠したあげくに、大時代的なタイトルの文藝同人誌をきまぐれなサイクルで発刊していた仲間の一人であるからには、その指示が彼の呟きからもたらされたものである可能性は確かに否定できない。Aはきっと、いまごろ同じように締め切りに追われながら原稿を書いているだろう。そしていつものように、締め切りに間に合わず、原稿を落とすかもしれない。しかし、ぼくが、発信者も定かでないその指示にあらがうこともできずにこの原稿を書こうとしているのは、ぼくに直接メールで指示をよこしたその人物に対して、ぼくが負い目をおっているからだ。もともとメールマガジンという形式の同人誌を発行しようと持ちかけたにもかかわらず、その人物にぼくは残りの仕事を押しつけて、いまではめったにメールボックスを開くこともない。しかし、こうした一連の心理描写は、単なる口実だという可能性もある。それ以上に、ぼくがこの仕事に魅惑され、引きつけられていたから、このやっかいな仕事を引き受けたのだという可能性についてぼくは考えてみる。しかし、いずれにせよそうしたいっさいの考察は無意味である。ぼくは指定された時間きっかりに到着する。すべては指示どおりだ。組織の指示にあらがうことはできない。
2008年3月3日号掲載
▲page
top